※このページにはプロモーションが含まれています
食品添加物を一切使わずだしと素材の力で多くの人々に全国で愛された「博多もつ鍋 浜や」。
現在全店舗が閉店し、店舗での味わいは過去のものとなりましたが、通販で購入できるセットには、「浜や」伝統の作り方を家庭でも失敗せず再現できるレシピが付属しており、通販ならではの本格的なもつ鍋を楽しめます。
本記事では、閉店の背景と「浜や」の魅力から、通販の選び方、品質・無添加だしへのこだわり、発注やキャンセルの注意点、野菜やしめの麺の準備方法、更に「前田屋」や「やま中」といった有名店との比較まで、初心者にも分かりやすく丁寧にご案内します。
なぜ「浜や」のだしは化学調味料なしでも旨いの?その秘密は?
「浜や」のもつ鍋が化学調味料なしで圧倒的な旨味を実現できる理由は、天然素材への徹底したこだわりと職人の技術にあります。
まずスープには背振山系の天然水を使用、花崗岩層を通してろ過されたミネラル豊富な地下水は、雑味がなく昆布やかつおなどから引くだしを引き立て、自然なコクと軽やかな旨味を生み出します。
更に、だしのベースは昆布とかつお節のグルタミン酸とイノシン酸が合わさることで、相乗効果で深い旨味を生む調合がなされています。
「浜や」では、化学調味料や着色料、保存料、増粘安定剤、調味料としての添加物を一切使用せず、数千回の試作を重ねた味の黄金比とレシピを完成させています。
また、スープづくりにかける手間も尋常ではなく、原料選定から温度管理、急速冷凍まで徹底し、素材の鮮度と旨味をぎゅっと閉じ込めることで、家庭で温め直しても風味が落ちにくい構成に。
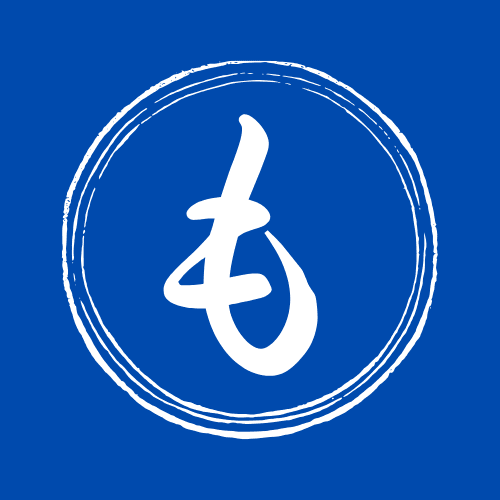
職人の技術と和食伝統の調理法が融合し、無添加でも満たされる味わいを実現しています。
更に、もつ鍋本体と野菜、そして「だし力」シリーズと呼ばれる調味料ラインも、すべて添加物ゼロ/化学調味料不使用設計です。
化学合成された甘味料・酸味料・香料・乳化剤・PH調整剤などを排し、素材本来の香りと味を生かす工夫が随所に施されています。
このような無添加への徹底は「健康面での安心感」と「自然な深い旨味」を両立し、子どもや健康志向の方にも安心して楽しめる鍋として支持され続けています。
また、無添加だからこそ昆布・かつおだしの風味が際立ち、もつや野菜が持つ甘みと調和した味わいが自宅で再現可能なのです。
まとめると、「浜や」のだしが化学調味料なしで旨い理由は以下の通りです。
-
軟水の天然水をベースに、昆布とかつお節の旨味成分(グルタミン酸+イノシン酸)を最大限に引き出す
-
数千回に及ぶ試作を繰り返し、最適なだしの調合を完成
-
全工程で無添加・無化調にこだわり、素材本来の旨味と安全性を追求
-
急速冷凍や徹底した温度管理により鮮度と味を維持
これらのこだわりが合わさって、「浜や」のもつ鍋は、化学調味料を一切使わずとも、自然の旨味と深みを感じられる絶品のだしに仕上がっているのです。
なぜ「浜や」は全店舗を閉店したの?その理由とは?
公式サイトにて「博多もつ処 浜やは全店舗閉店となりました」との発表がなされており、これにより実際に店舗へ足を運ぶ機会は完全に失われました。
食べログやRettyなどでも、博多駅前朝日ビル店をはじめ、すべての店舗が「現在閉店」の状態で情報として残っています。
閉店の明確な理由について、公式から詳しい背景説明はないものの複数の観点から推察可能です。
まず、飲食業界全体が近年、コロナ禍の影響や人手不足、原材料価格の高騰に直面していた点は見逃せず、特に地方店舗を展開していたブランドは固定費や物流コストの圧迫が厳しさを増していたと思われます。
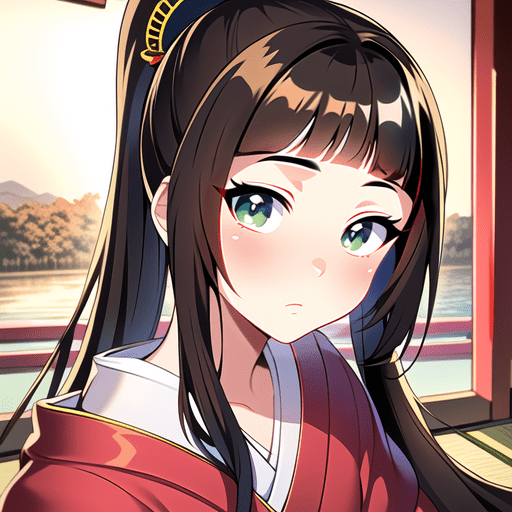
コロナ…許すまじ…!
また、「浜や」はこだわりの無添加だしや品質管理に多くの手間とコストをかけており、店舗運営よりも通販中心に切り替えることで効率や利益構造を見直した可能性が高いと感じます。
実際、公式通販サイトでは「三越伊勢丹バイヤーズセレクション認定」されるなど、通販に特化したブランド展開が明らかですが、個人的にはリアル店舗の維持に掛かるコストと、通販での効率を天秤に掛けた上で、後者に軸足を移した決断だったのではと推測します。
自分の印象としても、“品質第一”の姿勢は素晴らしい一方で、店舗での価格帯や立地、スタッフ教育などによる運営コストの肥大化が長期的には経営を難しくしたのではと感じます。
固定客が付いていたとはいえ、それでも足腰の強い本社や広域店舗網に頼らないと、持続しづらかったのかもしれません。
それでも閉店の告知が、「全店舗閉店となりました。足を運んでいただいたお客様に心より感謝致します」といった感謝の言葉とともに公式サイトでシンプルに伝えられていた点からも、運営側の顧客へのリスペクトと誠実さが感じられます。
更に新潟駅前店も含め、地方展開していた店舗が2023年2月頃までに閉店していたことを地域サイトが報じており、店舗運営の維持が厳しかった時期に計画的に整理を進めていたようにも思えます。
自分自身、「浜や」のもつ鍋を実店舗で味わえた経験があるだけに、閉店のニュースを聞い時はは正直とても残念でした。
ただ、それでも通販で味そのものを届けようとする姿勢がきちんと続いていることには或る種の安心感も覚えます。
総括すると、閉店には以下のような背景が考えられます。
-
コロナ禍後の飲食業界の厳しさ(人手不足・物流費の高騰)
-
品質にこだわる運営コストと収益構造の見直し
-
通販中心へ事業転換し、固定店舗の維持を断念
個人的には、閉店そのものよりも「店舗展開という形を通じて築いてきたブランド体験」を手放したことに寂しさを感じます。
ただ、今後も「浜や」の味を家庭で安心して再現できる通販という形で新たな魅力を発揮してくれる可能性に期待しています。
今でも買える?浜やのもつ鍋を通販で注文するにはどうする?
初心者でもできる?「浜や」のもつ鍋の作り方を分かりやすく解説!
「浜や」と他の人気もつ鍋店、どこが違う?前田屋・やま中と比べてみた!
「浜や」は店舗は閉店しましたが、無添加だしと通販による家庭向け提供で知られるブランドである一方、「前田屋」や「やま中」は今なお多くの人に愛される博多の人気もつ鍋店ですが、これら三者にどんな違いがあるのでしょうか?
まず、「前田屋」は福岡市内で今も営業を続ける人気店で、最高級の国産牛小腸を厳選して使用し、品質重視のスタイルが特徴です。
スープは味噌・醤油・ピリ辛の三種から選べ、あっさり系からこってり系まで対応、素材の旨味を生かした味わいで、しめまでじっくりと楽しめます。
一方、「やま中」は1984年創業の老舗で味噌味に特に定評があり、複数の九州産味噌をブレンドした濃厚スープが最大の魅力で、ぷりぷりのもつと相性抜群。
醤油味やしゃぶしゃぶ風といったバリエーションもあり、硬派な味噌派に支持され続けています。
対して、「浜や」は店舗営業ではなく、“もつ鍋の味”を通販によって提供している点が最大の違いです。
無添加・化学調味料不使用のだしと、家庭でも本格味を再現できる丁寧な作り方説明書をセットにした商品で、品質の安全性と調理の簡便さを重視していますが、これは健康志向の家庭などに大きく支持されています。
味・スープの比較
前田屋:あっさり系の醤油やピリ辛もつ鍋も選べるが、基本は素材の旨味を生かす控えめなスープ。
やま中:複数の味噌を使った濃厚なスープが特徴。コクとパンチのある味を求める人向け。
浜や:無添加だしにこだわり、昆布とかつお節をベースにした深い旨味。家庭でも飽きない自然な味わい。
もつの品質と食感
前田屋・やま中:どちらも九州産の牛小腸を使い、適度に脂の乗ったぷりぷり食感を重視。
浜や:品質へのこだわりは通販商品でも反映されており、国産素材を使用し、臭みなく柔らかい仕上がりを目指している。
提供スタイルの違い
「前田屋」や「やま中」は店舗での飲食体験を提供するスタイル。そのため、雰囲気や接客、店舗独自の一品料理など、現地の食事空間を楽しむことができます。一方「浜や」は、実際に店舗では味わえませんが、自宅でじっくり調理できる安心感と再現力がウリです。冷凍で届くため保存もしやすく、必要な分だけ調理できる手軽さも魅力です。
利便・入手性の差
前田屋ややま中:現地訪問が必要。予約必須のことも多く、観光や出張などタイミング合わせが必須。
浜や:通販で購入でき、遠方でも手軽に取り寄せ可能。解凍・調理手順もガイドされているため初心者にも優しい。
「やま中」は濃厚味噌スープと老舗の味、「前田屋」は品質重視でバリエが選べる上品なもつ鍋体験を提供。
「浜や」は店舗体験こそないものの、自宅で安心・安全なもつ鍋を楽しみたい層に最適な通販ブランドと言えます。
外で雰囲気と共に堪能するなら「前田屋」や「やま中」、家でじっくり味を再現したいなら「浜や」と選択肢が明確に分かれているのがそれぞれの魅力ですので、食のスタイルや目的に応じて自分に合ったブランドを選ぶのが良いでしょう。
まとめ
- 「浜や」はかつて人気を博したもつ鍋専門店で、現在は全店舗が閉店している
- 化学調味料を使わないだしが特徴で、素材本来の旨味が活きた味わいが支持されてきた
- 閉店の背景には経営判断や時代の変化、通販への注力など複合的な理由が考えられる
- 現在は通販を通じて「浜や」のもつ鍋を自宅で味わうことが可能
- 無添加のだしと高品質な国産もつを使用し、初心者でも簡単に美味しく調理できる
- 「前田屋」「やま中」などの有名店と比較しても、「浜や」は家庭向けとして独自の価値がある
- 外食での本格派を求めるなら他店、自宅で安心・安全に味わいたいなら「浜や」が最適
家庭でも本格的な味を楽しみたい方には、「浜や」のもつ鍋は非常におすすめです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
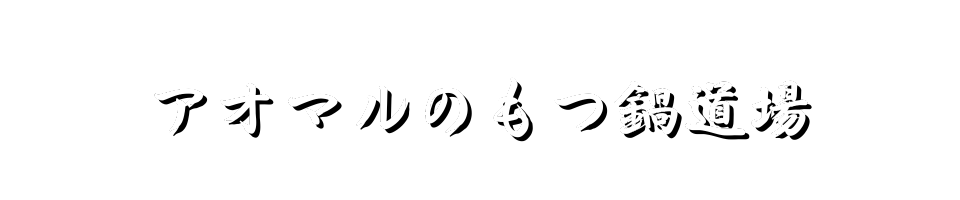
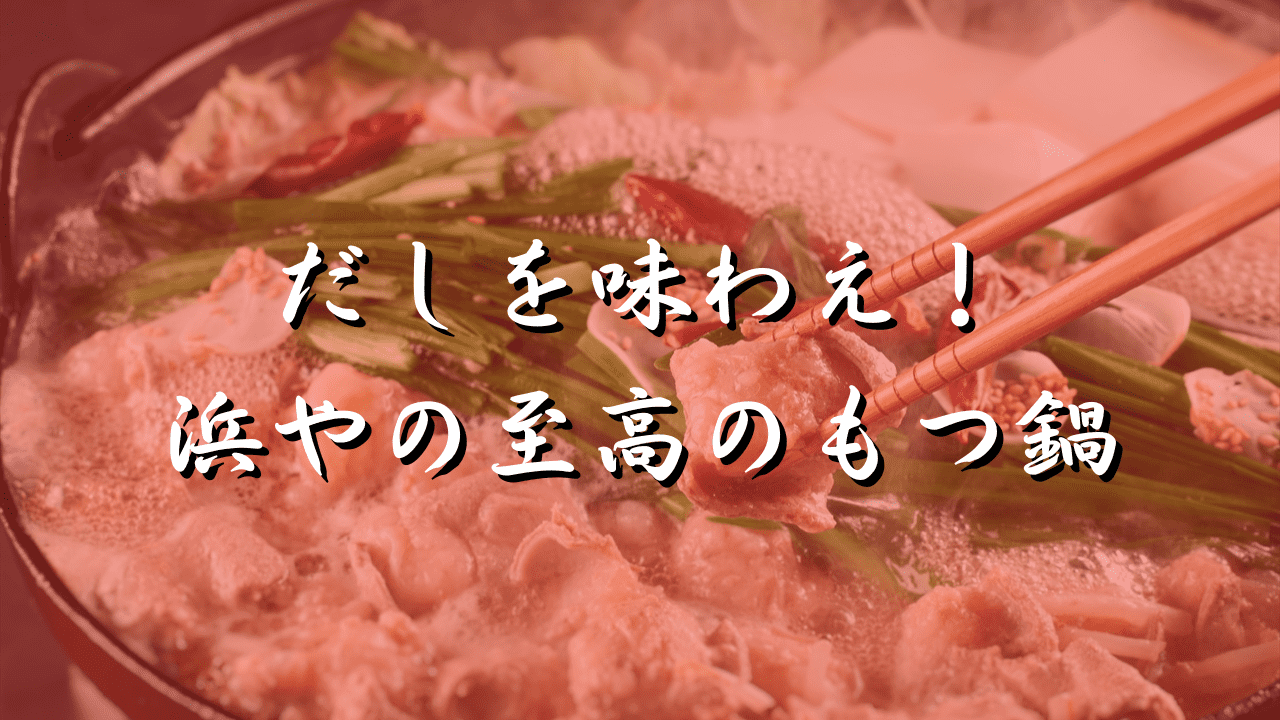


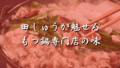
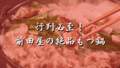
コメント